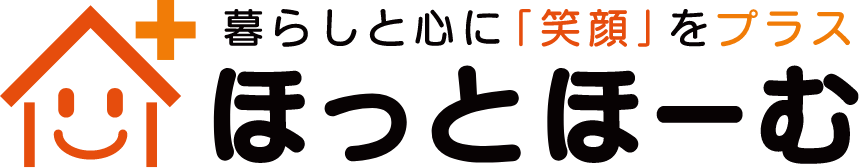断熱等級4は寒い?等級5・6・7の違いと快適な家づくりの選び方について解説します
これからマイホームを建てることを検討していて、断熱性能について詳しく知りたい、より快適な住まいを実現したいと考えている方へ。
2025年から新築住宅では断熱等級4が義務化されます。
しかし、快適な住まいを実現するためには、断熱等級4だけでなく、等級5、6、7などの高性能な住宅も検討する必要があるかもしれません。
断熱等級4は本当に寒いのでしょうか。
この記事では、断熱等級4、5、6、7の違いを分かりやすく解説し、それぞれの等級における快適性や光熱費、住宅の価値への影響を具体例を交えながら説明していきます。
将来の住まいの快適性と経済性を考慮した上で、最適な断熱等級を選択するための参考にしてください。
□断熱等級4の義務化と、快適な住まいを実現するための選択
2025年から新築住宅では断熱等級4が義務化されます。
これは、日本の住宅の断熱性能を向上させ、省エネ化を進めるための取り組みです。
しかし、断熱等級4はあくまでも最低基準であり、快適な住まいを実現するためには、さらに高い断熱性能を持つ住宅を選ぶことも検討する必要があります。
1:断熱等級とは。
断熱等級とは、住宅の断熱性能を評価する基準です。
等級が上がるほど断熱性能が高くなり、室温が安定しやすくなります。
2:断熱等級4のメリットとデメリット
断熱等級4は、法律で定められた最低基準ですが、室温の安定性や光熱費の削減効果は限定的です。
・メリット
-法律で定められた最低基準を満たすため、住宅の価値が下がることはありません。
-低価格帯の住宅を選ぶことができます。
・デメリット
-冬場は暖房費が高く、夏場は冷房が効きにくい場合があります。
-室内温度が安定しないため、快適な住まいを実現するには追加の費用が必要になる可能性があります。
3:断熱等級5、6、7を選ぶメリット
断熱等級5、6、7は、断熱等級4よりも高い断熱性能を持つ住宅です。
・メリット
-冬場は暖房費が抑えられ、夏場は冷房効率が向上するため、快適な室温を維持できます。
-光熱費の削減効果が高く、経済的な負担を軽減できます。
-室内温度が安定するため、結露が発生しにくく、カビやダニの発生を抑えられます。
-住宅の価値が高くなるため、将来的な売却時にも有利です。
4:断熱等級を選ぶポイント
断熱等級を選ぶ際には、以下の点を考慮する必要があります。
-住む地域の気候
-家族構成
-ライフスタイル
-予算
□断熱等級と住宅の快適性、光熱費の関係
断熱等級は、住宅の快適性や光熱費に大きな影響を与えます。
断熱等級4では、冬場は暖房費が高く、夏場の冷房も効きにくいため、快適な室温を維持するために追加の費用がかかる可能性があります。
一方、等級5、6、7では、室温が安定し、冷暖房費を大幅に削減できるだけでなく、住宅の価値も高くなります。
1:断熱等級と室温の関係
断熱等級が高いほど、室温が安定しやすくなります。
これは、断熱材によって外気温の影響を受けにくくなるためです。
・断熱等級4:室温は外気温の影響を受けやすく、冬場は暖房が効きにくく、夏場は冷房が効きにくい場合があります。
・断熱等級5、6、7:室温は外気温の影響を受けにくく、冬場は暖房費を抑えられ、夏場は冷房効率が向上します。
2:断熱等級と光熱費の関係
断熱等級が高いほど、光熱費を削減できます。
これは、室温が安定することで、暖房や冷房の使用時間を短縮できるためです。
・断熱等級4:暖房や冷房の使用時間が長くなるため、光熱費が高くなる可能性があります。
・断熱等級5、6、7:暖房や冷房の使用時間が短縮できるため、光熱費を大幅に削減できます。
3:断熱等級と住宅の価値の関係
断熱等級が高いほど、住宅の価値が高くなります。
これは、断熱性能の高い住宅は、快適性が高く、光熱費を削減できるため、市場価値が高くなるためです。
□まとめ
断熱等級4は、法律で定められた最低基準であり、快適な住まいを実現するためには、さらに高い断熱性能を持つ住宅を選ぶことを検討する必要があります。
断熱等級5、6、7は、断熱等級4よりも高い断熱性能を持つ住宅であり、室温が安定し、光熱費を削減できるだけでなく、住宅の価値も高くなります。
断熱等級を選ぶ際には、住む地域の気候、家族構成、ライフスタイル、予算などを考慮し、最適な等級を選択することが重要です。
当社は姫路市周辺で注文住宅を手掛けております。
建設業だけでなく不動産業のライセンスも持っており、土地選びからお客様の理想の住まいの完成まで、ワンストップでサポートしています。
家づくりに欠かせない土地の選定や資金計画も一緒に考え、安心して夢のマイホームを実現できる体制を整えていますので、家づくりを検討されている方はぜひお気軽にお問い合わせください。